| 「節分」 (2月3日) |
|
季節の移り変わる時期には厄災や疫病が増えるため、それらを鬼に例えて追い払う「追灘」と言う儀式がありました。鬼に向かって豆をまく風習はこれに由来していると言われます。 節分の日の夕方、「節分豆」として煎った大豆を神棚に供え、年男か厄年の男性が「鬼は外」と2回唱えながら玄関から外に向かって豆をまき、次に「福は内」と2回唱えながら家の中に豆をまきます。豆をまいた後は福が出て行かないよう戸を閉め、「今年も無病息災であるように」と願いながら家族がそれぞれの年の数だけ豆を食べます。 地域によっては、いわしの頭をひいらぎの枝に刺して、玄関や軒下に飾る邪気払いの風習があります。また最近では、細めの巻き寿司を丸ごと1本持ち、その年の恵方を向いて食べる習慣も広まっているようです。 また、数え年で厄年にあたる人はこの日に厄落としの儀式をすることが多いようです。神社でお祓いを受け、祝詞を上げてもらいます。その夜には家族や親戚、知人を招いて宴を開きます。来訪した人で厄を分け合い、持ち帰ってもらうことで災厄を払おうという意味があります。 |
 「節分」は、季節が分かれる節目と言う意味。立春、立夏、立秋、立冬の前日を指しますが、現在では特に立春の前日を節分と言うようになっています。冬から春になる立春は、古くは1年の境として考えられていたからです。
「節分」は、季節が分かれる節目と言う意味。立春、立夏、立秋、立冬の前日を指しますが、現在では特に立春の前日を節分と言うようになっています。冬から春になる立春は、古くは1年の境として考えられていたからです。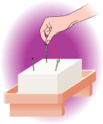 針供養の由来と歴史的背景は、遠く江戸時代に、京都にで針仕事をする人が、一日仕事を休んで、折れた針や使い古した針に、感謝を捧げる風習が始まりました。そして、この風習が、各地方の特殊なしきたりや宗教的背景と結び付き、それぞれ特異な形で発展してきました。しかし全般的にみれば、これらはお仕事始めの日から始まり、針供養の行事と平行して行われたのが基本である。供養は一般に、古い針や折れた針を紙に包んで、あるいは豆腐やこんにゃく等に刺して、海や川に流したり、神仏に供えて裁縫上達を祈願していました。
針供養の由来と歴史的背景は、遠く江戸時代に、京都にで針仕事をする人が、一日仕事を休んで、折れた針や使い古した針に、感謝を捧げる風習が始まりました。そして、この風習が、各地方の特殊なしきたりや宗教的背景と結び付き、それぞれ特異な形で発展してきました。しかし全般的にみれば、これらはお仕事始めの日から始まり、針供養の行事と平行して行われたのが基本である。供養は一般に、古い針や折れた針を紙に包んで、あるいは豆腐やこんにゃく等に刺して、海や川に流したり、神仏に供えて裁縫上達を祈願していました。
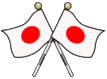 10月)改めて逆換算してみたところ、2/11が正しいという事になったようです。
10月)改めて逆換算してみたところ、2/11が正しいという事になったようです。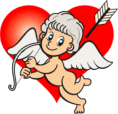 いまやバレンタインデーには盛大にチョコレートが送られますがこれは日本独特のもの。会社や学校では日常のお礼として、義理チョコも盛んに送られていますが、普通は夫婦や恋人同士でちょっとしたプレゼントにカードを添え、まごころをこめてお贈り物をします。
いまやバレンタインデーには盛大にチョコレートが送られますがこれは日本独特のもの。会社や学校では日常のお礼として、義理チョコも盛んに送られていますが、普通は夫婦や恋人同士でちょっとしたプレゼントにカードを添え、まごころをこめてお贈り物をします。