| 「ひな祭り」 (3月3日) |
|
|
|
お雛様 |
|
平安時代、宮中の幼い姫たちが紙や布、草などでつくった人形であそんでいたのが、ひな人形の始まりと言われています。人形には厄払いなどの意味がこめられ、3月初めの巳の日に、人形に汚れや禍いを移し、川や海に流して自分の身を清めたと伝えられています。 |
03月の行事
| 「ひな祭り」 (3月3日) |
|
|
|
お雛様 |
|
平安時代、宮中の幼い姫たちが紙や布、草などでつくった人形であそんでいたのが、ひな人形の始まりと言われています。人形には厄払いなどの意味がこめられ、3月初めの巳の日に、人形に汚れや禍いを移し、川や海に流して自分の身を清めたと伝えられています。 |
| 「春分の日」 (3月21日) |
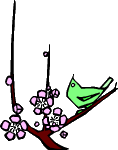 明治初期に春分の日が「春季皇霊祭」という国家の祭日になりました。 明治初期に春分の日が「春季皇霊祭」という国家の祭日になりました。第二次大戦後の1948年7月、公布・施行の祝日法によって制定されました。国民の祝日となり、春分の日は「生物をたたえ、自然をいつくしむ日」とされています。 春分の日は、その前年に国立天文台が発表する『暦象年表』という小冊子に基づいて閣議で決定され、前年2月1日の官報で発表されます。よって、2年後以降の春分の日・秋分の日は確定していません。 また、この日太陽は真東より昇り真西に沈み、昼と夜の時間がほぼ等しくなる。彼岸の中日でもあります。 |
|
|
|
Copyright (C) 2003 b-post.com. All Rights Reserved. |