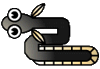| 「七夕」 (7月7日) |
| ~・ 一般的なお話 ・ ~ |
 むかしむかし、天の神様である天帝には織女という美しい娘がおりました。天の川の西に天界の機を織る織女は、神様たちのために素晴らしい着物を作ります。織女が毎日忙しく織物をしているのを見た天帝は、対岸に住む牛飼いの「牽牛」と結婚させ天の川の東で暮らさせることにしました。 むかしむかし、天の神様である天帝には織女という美しい娘がおりました。天の川の西に天界の機を織る織女は、神様たちのために素晴らしい着物を作ります。織女が毎日忙しく織物をしているのを見た天帝は、対岸に住む牛飼いの「牽牛」と結婚させ天の川の東で暮らさせることにしました。ところがどうしたことでしょう。二人は遊んでばかりいて、仕事を怠けるようになってしまったのです。このままでは、神様たちの着物はどんどんボロボロになり、牛たちも世話を受けられずに病気になってしまいます。織女の幸せそうな姿を嬉しく思っていた天帝も、これにはとても怒りました。そして、二人を天の川の両岸に引き離したのです。すると織女は毎日泣いてばかりです。気の毒に思った天帝は、1年に1度7月7日だけ、織女が天の川を渡って二人が逢うことを許したと言う事です。 |
| ~・ 鹿児島県喜界島の七夕のお話 ・~ |
1人の若い牛飼いがいました。姉妹の天女が天から降りて、泉の傍らの木に「飛羽」を掛けて、水浴をしているところを見つけて、その飛羽の1つを隠したのです。姉は驚いて飛んで天に帰りましたが、妹は牛飼いが飛羽をかえしてくれないの で、困ってとうとうその牛飼いのお嫁になりました。 で、困ってとうとうその牛飼いのお嫁になりました。数年後二人は、天とうへ親見参に行くことになりました。飛羽をつけ夫を抱えて飛びながら「私といつまでも一緒にいたいなら親たちが縦に切れと言うのを横に切りなさい」と約束させました。 天とうではキュウリの季節で、二人にキュウリを取ってきて出したのです。牛飼いが包丁を持っているときに、不意に親が縦に切れと言ったので、うっかりキュウリを縦に切ってしまいました。すると二人の間に川が出来て、天女と牛飼は両岸に分かれてしまいました。その日が7月7日で、その日以来二人は1年に一度、この日ではなくては逢えなくなってしまいました。 |
|
年中行事覚書・柳田國男 |
 「海の日」は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」として平成8年、国民の祝日となりました。
「海の日」は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」として平成8年、国民の祝日となりました。